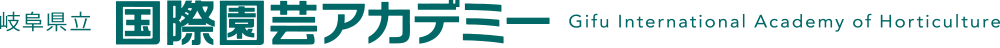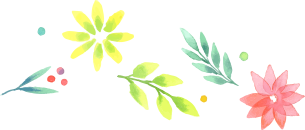今年も変化咲き朝顔が開花しました
2年生の「基礎育種学」で育てている変化咲き朝顔が今年も開花しました。変化咲き朝顔は、江戸時代後期(1810~1850年頃)に盛んに作出され、様々な珍品・奇品が生まれ、現代までその一部の品種が受け継がれています。写真は「采咲き(さいざき)」というタイプの変化咲きで、本来ならラッパ状に合弁する5枚の花弁が、合弁せずに開花します。この変化咲き朝顔は、実は種子ができません。では、どのように江戸時代から現代まで品種が受け継がれてきたのでしょうか?遺伝的には、普通咲き(丸咲き)は優性(A)、変化咲きは劣性(a)で、メンデルの遺伝法則によるところの劣性遺伝子をホモで持つ個体(aa)のみが変化咲きとなります。一方、変化咲き朝顔の兄弟株として出てくる普通咲き(AAまたはAa)は正常な種子ができます。普通咲きのうちのヘテロ(Aa)の株を自家受粉させてできた種は、メンデルの遺伝法則から1/4が変化咲き(aa)となります。そこで、変化咲きの兄弟株のうち、正常な花をつけ、種子を付けることのできる親木と呼ばれる朝顔を継代することで変化咲の系統を保存しているのです。まだ、メンデルが遺伝の法則を発表する前から、江戸時代の日本人は経験則として遺伝の様式を理解していたのでしょう。